記事内に広告を含む場合があります
当サイトの記事内では「アフィリエイト広告」などの広告を掲載している場合があります。2023年10月1日から始まる消費者庁「ステマ規制」にあわせ、読者の誤認とならないようにコンテンツ制作を心掛けていますので、ご安心ください。
また、問題のある表現がありましたら、お問い合わせより該当の箇所と併せてご一報頂けますと幸いです。


当サイトの記事内では「アフィリエイト広告」などの広告を掲載している場合があります。2023年10月1日から始まる消費者庁「ステマ規制」にあわせ、読者の誤認とならないようにコンテンツ制作を心掛けていますので、ご安心ください。
また、問題のある表現がありましたら、お問い合わせより該当の箇所と併せてご一報頂けますと幸いです。
「製造業はやめとけ!」
割と聞く言葉ですが、本当に経験者の意見なのでしょうか?イメージだけで言ってる人も多いと思うんですよね。
確かに製造業にはきついことはあります。でも仕事ってなんでもきついところもあれば良いところもあります。
製造業も同じで、きついこともあれば他にはないメリットも割とあります。
ここで結論ですが、『製造業のメリットに魅力を感じないならやめとけ』です。逆に言えばデメリットが気にならない人は向いているとも言えます。
というわけで、製造業のメリットとデメリットを詳しく解説していきます。この記事を読めば製造業とあなたの相性がわかるはずです。是非参考にしてください。
常に転職活動をしているので、いつのまにかキャリアアップ方法に詳しくなっていました。

一般的に製造業がやめとけと言われているのは以下の9個が理由です。
 コテツ
コテツこれを見ると製造業って最悪な仕事では…?



先に言っておくと誤解も混じっているよ!
ひとまず世間のイメージを見ていこうか!
製造業の労働環境は、高温や騒音、振動や粉じんなど、他の業界に比べて過酷である場合が多く、体力的な負担が大きくなることが考えられます。



夏とかマジできついっすよ…。
また、重い物を持ち運ぶ作業や、精密な作業を長時間行うこともあります。
製造業界は年功序列で昇進していく風潮が残っている企業が多いため、頑張って貢献しても思ったような評価が得られない場合があります。



納得のいかない人事評価は製造業界のあるあるです。
頑張った見返りが少ないため、次第にモチベーションが下がっていき、仕事がつまらなく感じる人は少なくありません。
ただ、逆に言うとそこまで頑張らなくても経験年数と共に昇格できるというメリットとして受け止められる人もおおいかもしれません。
製造業はライン作業などの”繰り返し作業”がメインとなる場合が多いです。
しかもその繰り返し作業は単純な作業なため、製造業はスキルが身に付きにくいというデメリットがあります。



どんどんキャリアアップしていきたい人だと将来が不安になりますよね。
しかし、このスキル問題に関しては解決可能です。以下の記事で詳しく紹介しているのでこちらも読んでみてください。
製造業は正社員の他に、企業によっては契約期間が決められている期間工も多くいます。
評価されれば契約満了後に正社員として雇用されますが、最悪の場合職を失ってしまいます。
上記に加え、製造業には技術の進化による人件費削減を目的としたリストラもあり得ます。



AIやロボット技術の導入により、人手を必要としない生産ラインが増加しているからです。
とはいえ、まだまだ人の手は必要です。しかし、技術の進化は早く、完全自動化を実現する日もそう遠くないかもしれません。
詳しくはこちら>>工場勤務の末路は体壊すか職失う?今から対策しないとやばい!
製造業は生産を止めないために交代勤務を採用している企業が多いため、夜勤を行う可能性が高いです。
日勤と夜勤を繰り返す交代勤務は、睡眠不足や食生活の乱れに繋がり、健康に良くありません。
人間は慣れる生き物なので、このリズムにはそのうち順応できますが、それでも体に良いことではありません。



一部では夜勤は寿命を縮めるとも言われています。
機械に巻き込まれる、クレーンで吊った製品が落下する、重機に轢かれるなど、製造業では怪我をする危険も付きまといます。
仕事中に負った怪我の治療は会社が負担してくれるとはいえ、後遺症の残る怪我をしてしまえば人生が終わってしまうこともあります。



近年の安全意識は高まっていますが、やはり危険であることは否定できません。
製造業は未経験でも採用されやすく、悪く言えば『誰でも入れます』
そのため、性格の悪い人、変わった人、不潔な人など、ぶっちゃけあまり関わりたくない人が少なくありません。



同じチームやコンビを組むことがあればストレスが溜まっていくでしょう…。
製造業の作業中はほぼ機械と向き合うことになるため、職場の人とのコミュニケーションが少ない傾向にあります。客先との会話なんてほぼないことも。
そのため、人と話すことが好きな人にとっては大きなストレスの原因となります。



一日の大半を過ごす仕事を楽しく過ごすために、コミュニケーションを重要視する人はきっと多いですよね。
製造業はデメリットばかりではありません。以下のようなメリットもあります。
特にワークライフバランスを重視する人に非常におすすめの業界です。
製造業の最大の強みと言えるのが”ワークライフバランス”の良さ。
上記の点からプライベートが充実します。
僕自身も土日祝休みで残業なんて月に0のときもあります。家族や友人との時間がたくさん取れるのは幸せです。



仕事だけで人生終わりたくない!そんな人にとって大きなメリットです。
しかも製造業は休みが多い割に給料は悪くありません。
残業代もしっかり出ますし、仮に夜勤があればその分手当てが付いて更に給料は上がります。



このことから、製造業はまさにワークライフバランスの鬼なんです。
製造業でゴリゴリ稼ぐなら>>2交代制はやめとけ!交代勤務は辞めとけ!その意見真に受けるの?
製造業は面倒な客先とのやり取りはおろか、同僚との会話だってしなくても仕事ができます。



人との会話が苦手、一人で黙々と作業したい。という人とっては天国のような環境です。
製造業は未経験でも採用されやすい業界代表ともいえます。
学歴や職務経験も問わないですし、マニュアルが充実していて仕事に慣れるのが早いからです。



教育制度も充実していて未経験でもしっかり育成してくれるので安心できますよ。
製造業がやめとけと言われる理由を説明しましたが、中には誤解も混じっています。



明らかに製造業で働いたことないだろ!っていう意見も混じっていますからね。



イメージだけでやめとけと言う人っているのよね…。
以前に製造業(工場勤務)に転職経験のある100人の方へ「工場に転職して良かった?」とアンケートを取ったことがあります。
結果、80人の方が「はい」と答えました。その理由はさまざまですが、多くの方が「人との関わりが少ないから」と答えました。
製造業は、「バリバリ働いて出世するぞ!」という方にはやりがいを感じにくいからやめとけと言えますが、そうでない人にとっては天国のような仕事です。



世の中にはいろいろな人がいます。製造業が天職の人もいるわけです。
アンケートでは工場に転職して良かったことや後悔していること、工場への転職が向いている人などを質問しています。気になる方は読んでみてください。


製造業に向いている人の特徴は「デメリットよりメリットが大きい!」と受け取った人はもちろんですが、以下に当てはまればなお向いていると言えます。
まあそりゃそうだわなって感じかもしれませんが、製造業で楽しく働くために重要な才能です。
ちなみに、コミュニケーション能力があるというのは会話を盛り上げられるということではありません。
たしかにその能力があるに越したことはありませんが、重要なのは報連相ができるということです。



製造業は報連相が不足していても回る仕事である場合が多いですが、その分、報連相を徹底しているだけで高評価を得られます!
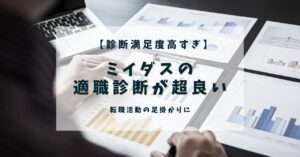
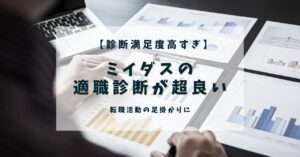
製造業といっても全てが同じような仕事ではありません。
工場で汗水流して働く職種もあれば、事務所での管理業務が多い職種だってあります。



どちらが良いとは言えません。人によって合う合わないがありますからね。
製造業の職種については以下の記事で解説しています。
ここで製造業のメリットとデメリットをおさらいします。
ここまで読んで、メリットが自分に合っているから工場勤務をやってみようかな!と思った人に一言。
会社選びを妥協するな…!
例えばブラック企業で工場勤務を始めたとします。
上記のメリットが消し飛ぶ可能性がございます。ええ。
逆にホワイト企業に入れれば例え交代勤務だとしてもデメリットを限りなく小さくできます。もしかすると消滅するかもしれません。



それほど会社選びは重要です。
とはいえ良い会社を見極めるのは難しいです。
じゃあどうすればいいのか。
答えは『信頼できる転職サイトや転職エージェントを利用する』です。
仕事を探すとなれば上記の方法は基本ですが、無数にあるサイトの中から自分で選ばなくてはいけません。
中には悪徳な業者もあり、とりあえずブラック企業でもなんでもいいから入社させて報酬を得ようとする業者だって存在します。
良い会社に入る=良い転職サイトやエージェントを利用する
これが大事です。
以下の記事でおすすめの転職サービスを紹介しています。どれも信頼できるおすすめなので、ぜひ参考にしてください。
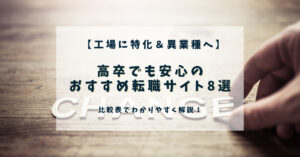
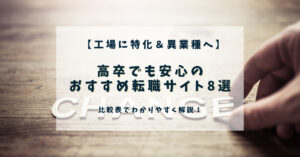
製造業にはやめとけと言われるデメリットがあるのは事実です。
その反面メリットもあり、人によってはそちらの方が大きく、実際製造業に満足している人は結構多いです。
製造業に興味があるのなら、さっきも話したように”会社選びは妥協しない”でください。それだけで全く待遇が違います。
今回は以上です。