記事内に広告を含む場合があります
当サイトの記事内では「アフィリエイト広告」などの広告を掲載している場合があります。2023年10月1日から始まる消費者庁「ステマ規制」にあわせ、読者の誤認とならないようにコンテンツ制作を心掛けていますので、ご安心ください。
また、問題のある表現がありましたら、お問い合わせより該当の箇所と併せてご一報頂けますと幸いです。


当サイトの記事内では「アフィリエイト広告」などの広告を掲載している場合があります。2023年10月1日から始まる消費者庁「ステマ規制」にあわせ、読者の誤認とならないようにコンテンツ制作を心掛けていますので、ご安心ください。
また、問題のある表現がありましたら、お問い合わせより該当の箇所と併せてご一報頂けますと幸いです。
製缶と溶接、どちらも鉄工構造物を作る上で欠かせない工程ですが、具体的な違いがわからない方もいるでしょう。
それぞれは密接な関係にありますが、根本的に作業内容が違います。
また、製缶と溶接はどちらも専門的なスキルや経験が必要なため、分担して人員配置している会社もあれば一貫して行う方針の会社もあります。
この記事では製缶と溶接の違いについて解説すると同時に、それぞれのポイントも解説します。鉄工業に興味がある方は是非参考にしてください。
常に転職活動をしているので、いつのまにかキャリアアップ方法に詳しくなっていました。

製缶と溶接は同じ鉄工作業ですが全く違う工程です。それぞれの役割を説明します。
製缶とは、タンクや建設資材、配管などの鉄工構造物を与えられた図面通りの形状に加工していく工程です。必要に応じて曲げや切削、ガス切断などの加工技術を駆使して製品を形にしていきます。
 テツオ
テツオプラモデルを鉄で作るイメージと言えばわかりやすいでしょうか。
簡単な構造のものから時には複雑な構造の製品まで、製作前の計画段階から全容を把握し、無駄なく製作するためには経験と技術が必要となります。
製缶について詳しくはこちら>>製缶工とは?仕事内容やきつい点と将来性を経験12年のプロが解説
溶接は、簡単に説明すると鉄同士を溶かしてくっつける作業です。チーズを焼いてとろけさせ、くっつけるようなイメージと言うべきでしょうか。
溶接にはいくつか種類があり、製品によって方法を選定する必要があります。また、実力の差が現れやすい作業で、上手な人の溶接は見惚れるほど綺麗に仕上がります。
たくさんの資格種類があることや、溶接技術を競う地区大会や全国大会があることから、鉄工業=溶接というイメージを持つ人も多いでしょう。



認知度が高いのは確実にこちらですね。
溶接について詳しくはこちら>>溶接とは?メリットとデメリットや種類を初心者向けに解説!
製缶と溶接は密接な関係にあり、製品を作る上でどちらも重要な工程です。
基本的に鉄工構造物を作る流れは上記となります。
組み上げる精度が悪いと部材間に隙間や段差が生まれ、溶接に支障が出ます。逆にせっかく綺麗に組み上げても溶接が悪いと外観が悪く強度も弱くなってしまいます。
このように、製缶と溶接のどちらかが疎かになると良い製品は作れません。



もちろんどちらかのみで完結する仕事もあります!
製缶と溶接、それぞれの仕事をするうえで重要なポイントを解説します。
製缶は鉄工業の中でもマルチな能力を求められる役割です。
製缶に求められる能力は第一に材料を正確に加工出来る力です。
などなど、一流の製缶工になるにはさまざまな能力を身につけなければなりません。
とはいえ、多くの会社ではまず第一に簡単な図面から構造を理解し、その通りに製品を作るところから段階的に経験を積むようにするはずです。



僕も最初は単純な構造の製品から経験させてもらっていました。
製缶はものづくりにおいて頭脳のような存在です。一通りの経験を積んだ後は見積もりや客先とのやり取りなど、管理系の仕事も増えてくるでしょう。
溶接はただ鉄同士をくっつけるわけではありません。外観が綺麗であることや、割れの原因となる内部欠陥をいかに少なくするかが重要となります。
内部欠陥とは:溶かした鉄の中に不純物や空気のかたまりがあること。他にもさまざまな種類の欠陥がある。



上手い人と下手な人では見た目が全く違います。上手な溶接はまさに芸術です!
また、重要な製品の場合は溶接の検査を行います。検査で不合格となれば最悪の場合全てやり直しとなり、無駄なコストを発生させることとなります。



溶接の検査は外観から内部の欠陥を見るものまで多岐に渡ります。
他にも、溶接工は環境や材料、製品によって溶接方法を変える必要があります。
溶接のプロになるためには上記の溶接方法を遜色なく使いこなせるよう努力を重ね、技術を習得する必要があります。



これに加えてプロの溶接工は縦や横、仰向けなどどんな体勢でも溶接ができます。
多くの会社では、適正に応じて製缶工と溶接工に分かれているはずです。
製缶と溶接、どちらも一流になるには多大な経験と努力が必要であり、掛け持ちだと中途半端な技術を持った作業者が増えてしまうからです。
そのため、製缶のプロと溶接のプロが協力して製品を作るほうが質が上がりますし、仕事も効率良く回ります。



僕の職場も半々の割合でどちらかに特化しています!僕は製缶です!
会社によっては製缶から溶接まで一貫して行う場合があります。
“人員不足”や”製缶と溶接のどちらかはそこまで技術が必要ではない”など理由はいくつか考えられます。



規模の小さい会社にありがちかもしれません。
恐らく覚えることや練習することが多く苦労するでしょうが、経験豊富になれるのも事実です。乗り越えた先には本当のプロになった自分が待っているでしょう。
「どうせなら給料の高い鉄工所へ行きたい」
「色々な業種の求人と見比べたい」
「どの転職サイトを使えばいいかわからない」
こういった悩みを持つ方に向けて個人的におすすめの転職サイトを8つまとめた記事を書きました。
それぞれの特徴を表で比較しているので自分に合ったサイトがわかると思います。是非参考にしてください。
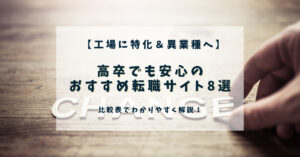
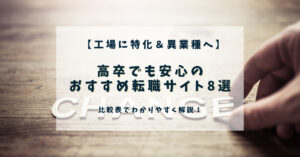
製缶や溶接に興味はあるが、そもそも自分に向いているのかわからない。という人もいると思います。
もしかすると、全く違う仕事が向いているかもしれません。
自分の適職を知るには自己分析が重要です。
そこでおすすめするのが、ミイダスという転職サイト内にある”コンピテンシー診断”というものです。
202問の質問に回答し、自分の適職がひと目でわかる仕組みとなっています。
無料登録で精度の高い診断を受けられるため、転職の軸を定めるヒントを得たい方は一度利用してみてください。



登録から診断終了まで、ざっと30分あれば終わります!
詳しく紹介している記事はこちら
製缶と溶接の違いを解説しました。
製缶と溶接は密接な関係にあり、製品を作る上でどちらも重要な工程です。
優劣は無いので自分が楽しいと思える、または適性があるほうを全力で極めましょう。
今回は以上です。